2024年に劇場または配信で公開された映画の個人的ベスト10とその感想です。下の方に個人的主演男優・女優、助演男優・女優賞なんかも。
10位:『スーパーマン』
監督:ジェームズ・ガン
異星人と排斥され傷つくスーパーマンが、侵略とジェノサイドに正面からNOを突きつけ、分断する世界から人々を救う。ジャーナリズムの意義も描きながら、底抜けの地獄のような現実や、あるいは血筋にも中指を立て、ただ善き人であろうと努力することを説いた直球のメッセージをしたためた一作。
9位『アイム・スティル・ヒア』
監督:ウォルター・サレス

軍事独裁政権下の70年代ブラジルを舞台にしたある家族の肖像。自分たち観客が舞台となる家と家族に愛着を抱くころ訪れる巨大な不条理。劇中印象的に登場する写真や8mmフィルム映像、なにより作品のタイトルが、喪失感もあの笑顔の記憶もすべて失われずここにあることを浮かび上がらせる。
8位『私たちが光と想うすべて』
監督:パヤル・カパーリヤー

大都会=ムンバイ自体が主人公であり、そこでの孤独や人生の無常感の飼い慣らし方と、同時に泣き出したくなる程美しい街の景色を捉える、どこかエドワード・ヤンを彷彿とさせる傑作。画面全体が青で統御される「都会」パートを経て、多様な色の光が溢れる奇跡のようなラストカット。
7位:『サブスタンス』
監督:コラリー・ファルジャ

エイジ&ルッキズムを内面化し消耗する主人公が辿る美と若さの地獄巡りは誰しも共感できる話でありつつ、その醜悪な規範の支持基盤である自分たち男性こそ身につまされるべき物語。物哀しさ・怒り・痛快さがないまぜになった、映画だから表現し得る「最狂」クライマックスの名状しがたい開放感。
6位:『旅と日々』
監督:三宅唱
一見益体もない会話や瞬間がなぜこんなに豊かに見えるのか。散文的な語り口の中にも、序盤と終盤で反復される「死んだ魚」のように、韻を踏むような心地よさが通底する。人が旅に出る理由すべてがこの中にあり、感想を言語化することすら無粋に思える、旅情そのものが映画体験として現れる一作。
5位:『ふつうの子ども』
監督:呉美保

呉美保監督の「普通じゃない」演出と編集で「普通の小学生」をリアルに生き生きと描いた傑作。実在感溢れる愛すべき主人公・唯士。自分がしでかした事態の大きさに後から気づき、それが起こる前の日々がなんとも愛しく思えてくる。誰しも経験のある成長痛が驚くべきほど生々しく、コミカルに響く。
4位:『ウェポンズ』
監督:ザック・クレッガー
ポスタービジュアルに象徴される「子供が走る姿」をはじめ、ホラー映画史に残る印象的アイコンを複数生み出しつつ、「依存という呪縛」的裏テーマがラストに至るまで完遂される傑作。どこに連れて行かれるか読めない不安感と高揚感が持続する、とにかく予備知識ゼロで観るのが望ましい一作。
3位:『We Live in Time/この時を生きて』
監督:ジョン・クローリー
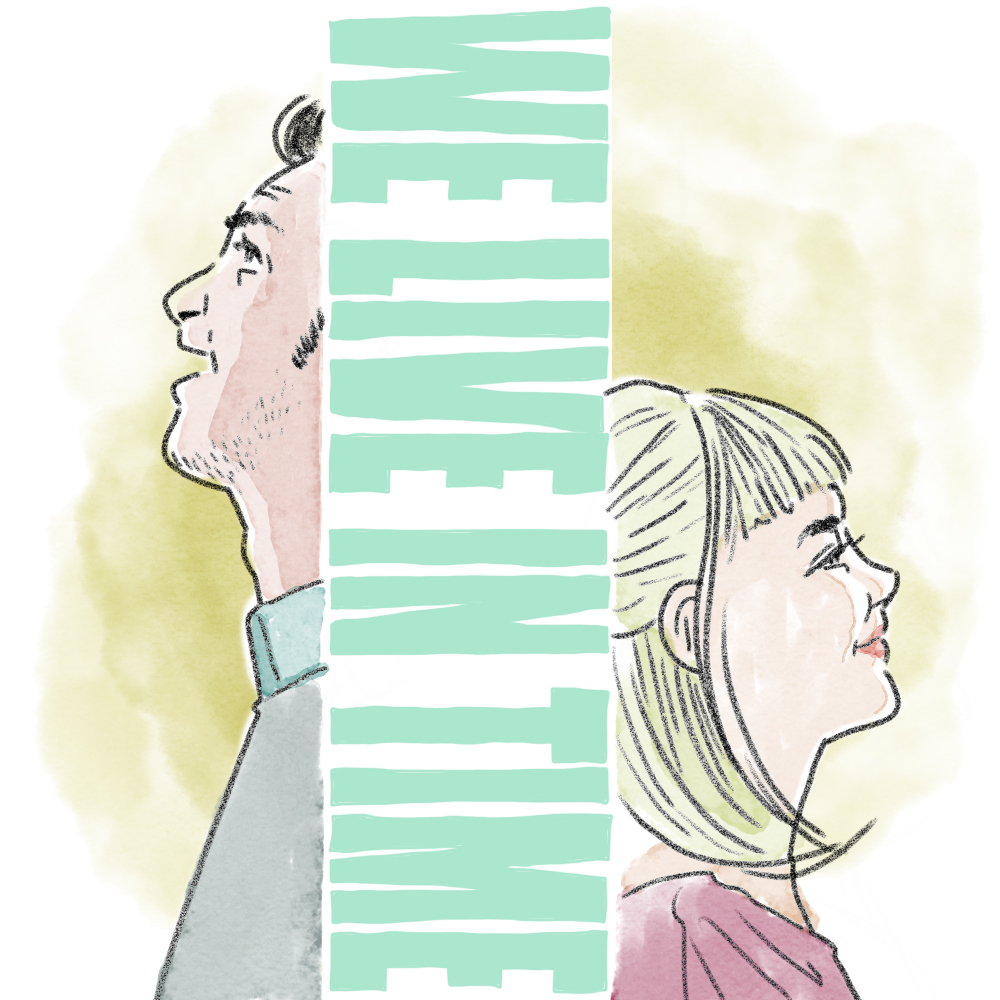
「ただ病気で死んだだけの母親と思われたくない」という主人公の想いを、映画の語り口自体が引き受け、「いわゆる余命モノ的感動」を断固拒絶する。至極の演技を見せる主演2人に止まらず、脇役に至るまで「その時」を確かに生きる。
2位:『ルノワール』
監督:早川千絵
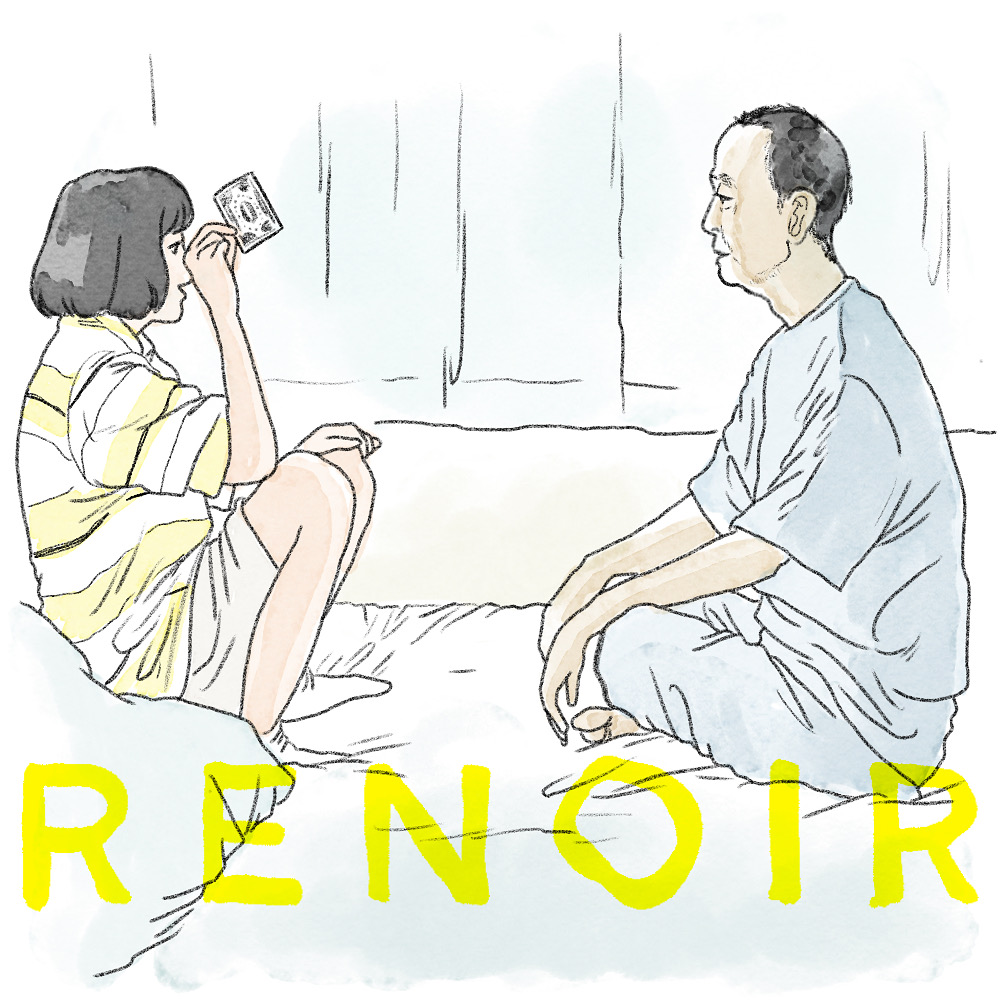
主人公・フキが生きる、ノスタルジーやエモとは異なる未成熟な80年代の日常を通して観客にとっての「あの頃」も呼び起こす。11才、マージナルな存在ならではの無邪気&残酷さで単色ではない世界を見つめる彼女の記憶にピン留めされるのは、オカルトや超能力を超えて他者と心を通わせるまでの瞬間の累積。
1位:『ワン・バトル・アフター・アナザー』
監督:ポール・トーマス・アンダーソン
爆笑必至の展開が続くのに、緊張感も全く弛緩せず、「最高に面白い映画を観ている多幸感」に浸り続ける最高の娯楽活劇。スクリーンの中で世界を救い続けるトム・クルーズもいれば、命綱なしで「情けなさ」の追求に飛び込むディカプリオがここにいる。
部門別
【主演女優賞】
シンシア・エリヴォ&アリアナ・グランデ(『ウィキッド ふたりの魔女』)
【主演男優賞】
セバスチャン・スタン(『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』)
【助演女優賞】
伊東蒼(『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は)
【助演男優賞】
ジェレミー・ストロング(『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』)
【ベストオープニング賞】
『ウェポンズ』
【ベストエンディング賞】
『入国審査』
【ベスト悪役賞】
フィリップ・ン(『トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦』)


コメントを残す